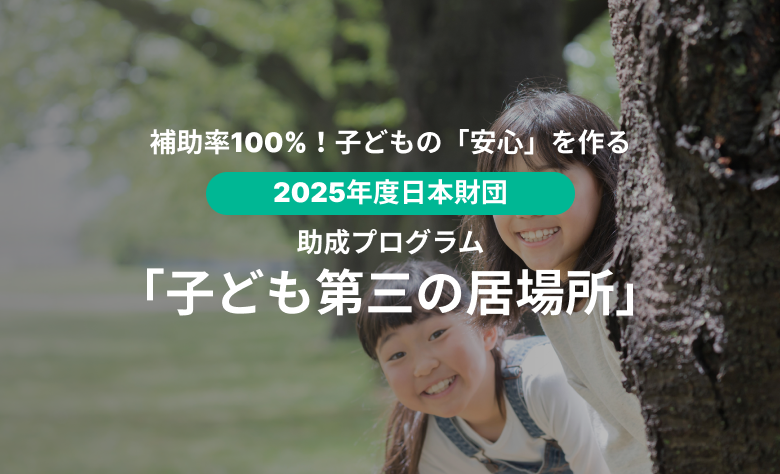
子どもたちが安心して過ごせる居場所として、「第三の居場所」「サードプレイス」の設置が進んでいます。子どもたちの「今」と「未来」を支えることは、大人世代の責任です。国内外の社会課題解決に取り組むNPOの事業への資金助成を行う日本財団では、第三の居場所の普及を促進するため、2025年度も「子ども第三の居場所」助成事業を設置しました。
今回は、日本財団の「子ども第三の居場所」助成事業の内容や申請方法をお伝えします。
▼▼▼補助金関連情報配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次
第三の居場所、サードプレイスとは?
家庭の抱える困難は複雑・深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、子どもが孤立するケースが後を絶ちません。特に放課後の時間に、家庭や学校以外で、子どもたちが安心して過ごせる場として設置されているのが「子ども第三の居場所」です。2024年7月末時点で、全国に233の拠点があります。
(日本財団:子ども第三の居場所)
子ども第三の居場所では、健康を支える食事や正しい生活リズムの構築、学習サポートまで、子どもに必要なあらゆる支援が行われています。また、個別相談を通じて保護者にも日常的なフォローを行うなど、包括的な「居場所」としても機能する場所です。子どもの抱える困難は、外からは見えにくいことが多い問題です。必要な支援につながれず、苦しい思いをしている子どももたくさんいます。関係機関が連携して子どもの状況を共有し、支援につなげるアウトリーチが必要です。
「子ども第三の居場所」は、学校や地域、専門機関と積極的に連携し、「誰一人取り残さない地域子育てコミュニティ」のハブとしての機能も担います。日本財団では子ども第三の居場所を通じて、地域、行政、NPO、市民、企業、研究者と協力し、「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会を目指しています。

日本財団:子ども第三の居場所
2025年度「子ども第三の居場所」助成事業の支援内容
日本財団では、「子ども第三の居場所」助成事業として、各地域で「子ども第三の居場所」の開設・運営を希望する団体を支援しています。まずは「子ども第三の居場所」助成事業の概要を見ていきましょう。
対象となるのは非営利活動・公益事業を行う団体
対象となるのは、日本国内で以下の法人格を取得し、非営利活動・公益事業を行う団体です。
| ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・公益財団法人 ・公益社団法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 |
なお、一般財団法人と一般社団法人については、非営利性が徹底された法人のみ対象となります。
対象事業は居場所の運営基盤を整える取組
子ども第三の居場所には、「常設(包括)ケアモデル」「学習・生活支援」「コミュニティモデル」の3種類の拠点があります。2025年度の事業では、「包括ケアモデル」の施設が助成の対象です。2024年度まで実施していた「コミュニティモデル」の募集はありませんので、注意してください。
対象となる事業と主な要件は、次の①~➂です。
| ①開設事業 | 「子ども第三の居場所」のための建物・空間の建築、改築、増築と、家電・家具・什器の購入を行う事業です。 【主な要件】 ・実施場所の延床面積は90㎡以上とし、定員数に合わせて十分な広さを確保すること ・実施場所は学校の近くなど、子どもが通いやすい立地であること ・食事提供や入浴支援を行うための設備を設けていること |
|---|---|
| ②車両整備事業 |
こどもを居場所へ送迎するために使用する、車両の購入費用を助成します。 【主な要件】 送迎のニーズがあり、居場所の運営時に日常的に送迎を行う必要があること なお、車両整備事業のみの申請はできません。 |
| ➂運営事業 |
以下のような、包括ケアモデルの施設が対象です。 ・週3~5日以上開所する ・ひとり親世帯における孤立や生活困窮世帯など困難を抱える子どもを対象とする ・個別の支援計画を立て、学習支援や生活支援、豊かな体験機会の提供、保護者への支援等を行う 【主な要件】 ・週3~5日以上の開所(週15~25時間以上の運営)であること 未就学児や不登校児に限定して日中のみ開所する場合は対象外です。 ・運営終了時刻は、原則として19時以降とすること ・原則として、経済状況や家庭環境に課題を抱える小学生低学年の児童を対象とすること ・登録者数は20名以上、1日あたりの利用児童は15名以上であること ・マネージャー(フルタイム)1名以上、パートタイムまたは、ボランティアスタッフが1日あたり2名以上の体制であること ・教育や保育等の現場経験者が2名以上いること なお、うち1名は経験年数が3年以上であることが必要です。 ・最長2年間の助成終了後は、児童育成支援拠点事業等の自治体の事業を受託して、団体が運営を継続すること ・実施場所の延床面積は原則90㎡以上とし、定員数に合わせて十分な広さを確保すること ・実施場所は学校の近くなど子どもが通いやすい立地であること ・食事提供や入浴支援を行うための設備を設けていること。。 |
対象経費
助成の対象となる費用は、以下のとおりです。
| ①開設事業 | ・実施設計費・建築に係る直接工事費・共通仮設費・現場管理費・設計管理費・居場所に設置する家電、家具、什器などの購入費 など |
|---|---|
| ②車両整備事業 | ・車両本体の購入・カーラッピング・ドライブレコーダー・バックモニター・自動ブレーキシステム・サイドバイザー・フロアマット・法定費用・任意自動車保険・登録諸費用 |
| ➂運営事業 | ・スタッフ、アルバイト等の人件費・給食費・水道光熱費・消耗品費・燃料費・諸謝金・通信運搬費・印刷製本費 など |
助成金額
補助率は100%です。ただし、開設事業は5000万円が上限です。
審査スケジュール
申請は、日本財団のホームページから行います。まだアカウントがない団体は、アカウントの新規作成を行って下さい。
そのほか、申請期間や審査のスケジュールは以下のとおりです。
申請期間・スケジュール
申請締切:2024年10月31日(木)17:00
| 審査期間 | 11月~2025年2月 |
|---|---|
| 審査結果のお知らせ・助成契約書の締結 | 3月 |
| 事業実施期間 | 2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火) |
申請時に必要な添付書類
|
■継続計画書・運営計画概要 ■自治体協力届出 ■前年度決算書類 ■当年度予算書類 ■定款 ■現況写真 なお、開設事業を実施する場合は以下の書類も必要です。 ■建築見積書 ■工事対象建物および土地の7年以上の確保が証明できる書類 ■工事対象建物および土地の登記簿謄本コピー |
審査でみられる3つの視点
申請後、以下の3つの視点から審査が行われます。
①組織・運営体制
・事業要件をすべて満たしているか
・養育環境に課題を抱える子どもへの学習支援事業や、居場所事業、自治体との連携実績があるか
・団体の財務状況は健全か
・本事業を安定的に継続できる財政基盤を有しているか
②事業の効果・モデル性
・多様な関係者と連携し、事業の社会的意義を高めるとともに効果的に実施する工夫があるか
・既存の子ども支援の事業・制度に対して、新たな価値を示したり、他地域への手本となるモデル性を有したりしているか。また、それを積極的に発信できるか
➂継続・発展性
・助成終了後においても同事業を継続、発展させていく能力があるか
・自治体による事業継続意思確認がとれているか
まとめ
子どもが健やかに、安心して過ごせる居場所を作ることは、社会全体にとっても重要なことです。一方で、一人親世帯や貧困家庭など、子どもを取り巻く問題は複雑さを増しています。家庭内の問題を保護者だけで解決することが、難しいケースも多いのです。
子どもの成長は、地域や、社会全体で支えるべきです。子ども第三の居場所は、他機関との連携や地域とのつながりを通じ、子どもを支える人を増やし、社会全体で見守る仕組みを作ることができる施設です。日本財団の「子ども第三の居場所」事業を始めとする支援策を積極的に活用し、より多くの地域に、子どもが安心できる場所を広げていきましょう。
▼▼▼補助金関連情報配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する





